

首都圏の都市部も地方の過疎地もひとつの“地域”。それぞれに解決すべき課題がある一方で、埋もれた価値があります。地方では農家や漁師の方と交流する機会もあり、人と触れ合うことで地域を知り、隠れた魅力を探し出して課題解決に役立てます。

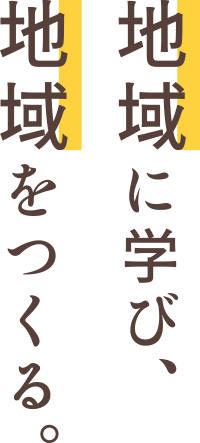

経済学や経営学の理論を地域で実践していく4年間。
地域住民との交流をとおして地域の課題を見極める洞察力を高め、企画力や実行力を磨きながら、課題解決や新たな価値の創出に挑むやりがいがあります。

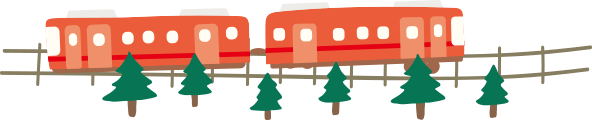

都市部や地方でさまざまな人とつながりながら、それぞれの地域の困りごとを解決する仕組みづくりや、イベント企画のための実践力を養います。
「地方創生」ではなく「地域創生」のため、東京をはじめとする首都圏も学びの対象になります。
 地域実習
地域実習
現地の産業や観光資源、自然環境を理解し現地の人々と協力して課題解決に挑戦


首都圏の都市部も地方の過疎地もひとつの“地域”。それぞれに解決すべき課題がある一方で、埋もれた価値があります。地方では農家や漁師の方と交流する機会もあり、人と触れ合うことで地域を知り、隠れた魅力を探し出して課題解決に役立てます。


私は高校時代から空き家問題に興味があり、「地域経済学」の授業で空き家の活用事例を学んだほか、「地域実習」では新潟県南魚沼市を訪れて、空き家の活用が進まない原因を探りました。現地では空き家に関わるさまざまな立場の方へのインタビューを行い、リアルな声を引き出すインタビュー調査の重要性を実感しました。その内容も参考にして、現在は自分で“空き家サイト”を開設。空き家を活用したプロジェクトを企画しながら、空き家の所有者と活用者をマッチングさせる仕組みをつくり上げたいと考えています。
地域創生学科 平野 彩音さん
 地域課題解決実践論
地域課題解決実践論
大学周辺“地域”で経済の活性化やにぎわいの創出にチャレンジ

地域性を意識したマーケティングリサーチや、広告や店頭での集客戦略の大切さは企業経営と同じ。流通の仕組みや、製品開発に必要な技術などを理解し、消費者目線での分析も加えた上で、地域の課題解決策を考えます。その過程で企画力や実行力が向上し、アントレプレナーシップ(起業家精神)が養われていきます。


私は「ガモール堂」でスムージーを販売する「地域課題解決実践論」のプロジェクトで、商品企画班のリーダーを務めています。フードロス削減と地域の特産品を結びつけるというテーマのもと、食材選びやレシピづくりで試行錯誤を繰り返し、これまでに長野県箕輪町や岐阜県飛騨市とコラボレーションしたスムージーなどを販売してきました。また、InstagramやFacebookでの情報発信も担当。今後は商品企画のプロセスのほか、インターネットを活用したSNSマーケティングについて専門的に学んでいきたいです。
地域創生学科 鷲田 勝喜さん
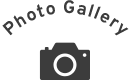



今、日本では都道府県から地域の市区町村に至る行政、企業、各種団体、そして日本で暮らす一人ひとりのつながりから生まれるネットワークの拡大が求められています。だからこそ、これからの社会を築いていくみなさんには、都市の視点で地域活性化に貢献し、それと同時に地方の視点で都市問題にアプローチできる力が必要になると大正大学は考えます。数週間にわたる長期の地域実習を軸に、都市と地方の双方に関わりを持ちながら、日本の未来を創造できる「地域人」を目指しましょう。
1年間を4学期に区分する「クォーター制」を採用。1年次から3年次までは、第3クォーターに実施される地域実習を軸に授業が組まれます。地域実習は1年次では首都圏実習、2年次と3年次では地方地域実習に取り組み、都市の視点と地方の視点の双方から地域の課題を発見する力を身に付け、実習準備は各学年の「フィールドワーク方法論」のアクティブラーニングで行います。

地域の課題解決における優れた実例に触れながら、フィールドワークの意義を理解し、チームビルディングや社会調査のスキルを高めます。調査・分析のための視点や、自分の言葉で他者に提示する報告書の書き方も学びます。

地域経済を担う中小企業の機能と役割を理解し、地域活性化に寄与する地域産業の育成や起業の在り方を分析。地域における起業計画の策定方法を学び、地域資源を活用して新たな価値を生む実際の計画づくりにも挑みます。

企業の「売れる仕組みづくり」や、実際のヒット商品や流行の事例から企業経営を分析。ニーズの特定や市場調査、ブランディング、販売促進、地域課題の解決など、マーケティングの基本的な概念と発想方法を体得します。

地域振興やまちづくりに関する地域経済学の理論を学び、少子高齢化や人口減少、高齢独居者の増加などに直面する地域の経済を分析。先進地域との比較も行いながら、地域価値の創造に向けた実践的な解決策を模索します。

民間非営利組織(NPO)や市民活動の社会的意義や役割を学習。設立・運営に必要なガバナンスや資金調達、人事・労務管理の手法など、豊富なケーススタディで理解を深めながら、非営利活動の可能性を探求します。

成長と再分配の両立を加味した経済政策の可能性を探るため、経済学における分析手法を学習。ミクロとマクロの双方の観点から政策から検討することで、今後の日本経済にいかなる政策が必要であるかを考察します。
地元に戻って働きたい、新たなビジネスで地域を変えたい、NPOで人の役に立ちたい。それぞれの目標やスタイルに合わせて、自分だけの未来を描けるように地域社会について経済学・経営学の観点から広く学びます。