学部・大学院FACULTY TAISHO
比較文化専攻
戦争と文化(11)――石川明人『戦争は人間的な営みである――戦争文化試論』に見られる「平和」論と「戦略」論
はじめに
先回のブログでは、キーガンの著作を導きとしながら、「平和」について考えた。今回は、この流れの中で、北海道大学の石川明人氏(宗教学・戦争論専攻)の新著『戦争は人間的な営みである――戦争文化試論』(並木書房、2012年)を取り上げたい。
『戦争は人間的な営みである』というタイトルの裏にあるもの
石川氏(以下「氏」と略記)は、次のように告白する――「一方では戦争の悲惨さと恐ろしさに対する涙があり、平和への思いがある。だが同時に、他方では、戦争・軍事に対する無邪気で軽薄な好奇心がある。これが私の正直な感覚なのである」。
また、本書の「戦争は人間的な営みである」というタイトルには、多くの読者が眉をひそめたり疑問をいだいたりするだろう――「著者は戦争肯定論者なのか?」「タイトルは、非人間的の〈非〉が抜けているのではないか?」「何を意味しているのか理解できない」…。 「告白」やタイトルから判断すると、本書は真面目な本ではないような印象をもたれるかもしれない(一般向けの本なので、学術書のような註もない)。
しかし、それはまったく違うのである。私が興味を引かれたのはメインタイトルではなく、「戦争文化試論」というサブタイトルである。どうして本書が生まれたかを理解するには、学説史的な説明が必要だろう。
 これまで、戦争や軍事に関する学問分野では、軍事行政・軍事史・戦略・戦術・軍事技術・国際関係などについて研究されてきた。しかし、近年の傾向として、戦争を「文化」として捉える傾向が強くなってきている。本ブログのタイトルは「戦争と文化」である。ここでも頻出するM・クレフェルトの『戦争文化論』の原題はThe Culture of War である。きちんと訳せば『戦争という文化』となる。
これまで、戦争や軍事に関する学問分野では、軍事行政・軍事史・戦略・戦術・軍事技術・国際関係などについて研究されてきた。しかし、近年の傾向として、戦争を「文化」として捉える傾向が強くなってきている。本ブログのタイトルは「戦争と文化」である。ここでも頻出するM・クレフェルトの『戦争文化論』の原題はThe Culture of War である。きちんと訳せば『戦争という文化』となる。
先回のブログで取り上げたJ・キーガンは『戦争の歴史』という本も書いているが、そこで、彼は戦争を「文化の表現/発露」と捉えている。つまり、「戦争という現象は、〔クラウゼヴィッツ的な〕政治といった狭義かつ合理的な枠組みの中では到底説明できるものではなく、より広義の文化という文脈の下で捉えることによって初めて理解できる」(石津朋之)というわけである。
実際に氏の『戦争は人間的な営みである』の中でも、クレフェルトやキーガンに言及されているし、彼らの影響も読みとれる(第3章「兵器という魅力的な道具」など)。本書は、そうした、世界的な戦争研究/軍事研究のパラダイムシフトの延長線上にある「真面目な」本である。タイトルへの疑問も、本書を読み終えれば、氷解するであろう。
ちなみに、本書の論述には2つの大前提がある。①軍事とは、良くも悪くも「文化」であり、戦争もまた、良くも悪くも「極めて人間的な営み」である。②戦争・軍事の研究は、究極的には、人間や社会のありように関する考察に他ならない。
そして、氏が奇妙なタイトルをつけたのは、「戦争は決して好ましいものではないが、それを行なっているのはあくまで私たち人間自身なのだから、〈悪〉の一言で切り捨てずに、それを正面から見つめなおそう」という提言をするためである。
石川氏の戦争教育観
石川氏の授業は戦争や軍事をテーマにしているが、大学では大人気の授業である(500人もの聴講生がいるそうだ)(註1)。本書でも書かれているように、「この大学で最大数の受講者を記録したこともある」。
これは日本の大学教育にとって重要な事実である。大学生は戦争について知りたがっているのである。しかしながら、わが国の大学(防衛大学などを除く)では、「平和」がキーワードになっている授業は少なくないが、戦争や軍事そのものについての授業は「極端に少ない」そうである。いわれてみれば、そうだろうなぁと思う。
氏によれば、「これまでの日本では、過去の戦争に対する〈反省〉のもとに、戦争や軍事については、とにかくひたすら〈否定〉することばかりがなされてきた」という。本書のタイトルに嫌悪感をもつ人々は、おそらくこうした教育の影響を間接的に受けているのだ。問題は戦争の否定に至るプロセスだ。戦争の悲惨さや悲しさといった「情緒」に訴えるだけが平和教育ではない。むしろ、「冷静な視点から〈戦争〉や〈軍事〉を学ぶこと」も、心底から平和を希求するのなら、重要である。
こうした氏の戦争教育観は、ある種の「平和主義」批判へとつながっていく。「ある種の」と限定をつけておくが、「冷静な視点から戦争や軍事を学ぶ」姿勢をもった平和主義なら、氏も認めるからだ。これを踏まえておいていただきたい。それでも、氏いわく、「戦争に対する〈反対〉は、それを叫ぶ本人のセンチメンタリズムを満足させるだけでしかない」、「戦争や軍事を、ただ頭から否定しさえすれば自分は〈平和主義者〉でいられるかのように振る舞うのは、怠慢であり、偽善である。平和主義の名を借りた思考停止に他ならない」。なかなか手厳しい。平和を手に入れたい/平和を実現したいのならば、戦争や軍事そのものをきちんと研究/勉強しなければならないのである。もちろん、それには程度の差はあるだろう。
氏は、戦争や軍事を無視する傾向にある現代日本の教育に対して、「日本のほとんどの大学・大学院が、極めて長い間これら〔戦争や軍事〕についての研究や教育を怠ってきたことを、未来の、真の平和主義者たちは、必ず批判するであろう」と警鐘をならしている。くり返しにもなるが、真の平和主義者になるためには、戦争や軍事についてしっかり学ばなければならないのだ。私も同感である。
また、いうまでもなく、戦争の形態には時代や地域において種々の形態がある。すべての戦争は時代の流れのなかで「新しい顔」で立ち現われてくるのである。だから、「平和主義とは、現在の戦争スタイルを十分に理解し、また近いうちに戦争が起こるとしたらそれはどういうスタイルの戦争になるかを予期して、それらについて反対することでなければ意味がない」。過去のスタイルの戦争に反対しても、それはナンセンスだということだ。そして、どんな戦争が到来するかを予知するためには、戦争について知る必要がある。また、国民全体で平和について考えるならば、日本の大学でも「一般教養」として戦争学の講座がもう少し開設されてもいいのではないか。
ついでながら、世界の多くの戦争研究者の一致した予想では、テロ、ゲリラ、低強度紛争(大規模な武力の使用が行なわれる通常戦争と、武力が使用されていない平和状態との中間に位置する紛争)などが、今後ますます一般的な戦争形態になるという。クラウゼヴィッツ的な「国家間の戦争」は、最近ではほとんど行なわれていない。これは、イランとイラクなど、ごく一部の国家間でしか起こっていないのである。
そして、将来的に戦争について考える時、「人文系学問の知」「文化論的視点」がますます重要になると推測される。宗教学者の知識も求められる可能性は高い。
戦争文化としての「憲法九条」
石川氏は、「憲法九条」も「戦争文化/軍事文化」の一部だと断言している。氏は「平和憲法 vs.戦争」という二項対立的な捉え方をせず、「戦争文化に平和憲法が組み込まれている」という捉え方をする。これは、憲法九条を平和の象徴と考えている多くの人々には奇異に響くかもしれない。そう断言する氏の理由は明快である――「九条は日本の軍事・自衛隊のありように、現に大きな影響を与えている以上、端的に現代日本の〈戦争文化〉、〈軍事文化〉の一部に他ならないから」である。また当然、九条はアメリカや周辺諸国の軍事にも影響を与えている。重要なことは、九条をセンチメンタルに〈平和主義〉の象徴として崇めることではなく、「良くも悪くも日本や周辺諸国の軍事に大きな影響を与えている戦争文化だと認識しておくこと」である。
20世紀の後半からは、「総力戦」の様相を呈した2つの世界大戦への反省もあり、「いかなる場合でも暴力や武力行使は好ましくない」という価値観が世界的に共有されるようになった。さらに、仮に戦争が起こったとしても、味方に対しても敵に対しても、「犠牲を最小限に抑える期待」が極めて高くなった。氏はこれを「戦争や軍事に関する、最近のかなり大きな変化の1つ」と捉え、「その最もラディカルな表現が、日本の憲法九条だった」と解釈する。少なくともこの意味において、憲法九条は当時の最先端をいく憲法なのだ。
|
戦艦大和(Wikipediaより) |
こうした見解の背後にあるのは、氏の念頭にある次のような影響関係である。戦争のスタイルが変化する⇒それによって人々の戦争観が変わる⇒それが戦争・軍事のあり方にフィードバックされ、社会のありよう〔憲法の内容もそこに含まれる〕にも影響を与える。こうした大きな流れの中で九条を理解することが大切である。
つまり、第二次世界大戦などへの反省により、人々の戦争観が変化した。それがフィードバックされて出来たのが、憲法九条だということだ。九条に対するアメリカの影響が議論されることもあるが、ひょっとしたら、日米2国を超えたレベルで、そうしたフィードバックが起こったのかもしれない。
しかしながら、この論理に従うと、「憲法九条は必然的に変えていくことになる」という結論に繋がらざるを得ないだろう。氏は、管見の限り、どこにも改憲論を呈示していないが、これは論理の必然である。おそらく、氏も改憲論者の立場にたつと予想される。もしもそうであれば、戦争文化論の観点からは、どのように憲法を変えるべきか、どのように憲法が変わっていくかを、知りたい気がする。
いずれにしても、「戦争文化試論」から導かれる「憲法九条は戦争文化の一部だ」という主張を、平和主義者も知っていた方がいいだろう。
「俗の極み」としての平和
本書の引用のなかで、私の印象にもっとも強く残ったものは、戦艦大和の沖縄特攻に参加し、奇跡的に生還した吉田満の次の言葉である。
終戦が来て、平和が訪れ、身辺が平静にかえるに従い、私は自分に欠けていたものを、漠然と感じはじめた。死に臨んでの、強靱な勇気とか、透徹した死生観とかが、欠けていたのではない。静かに緊張した、謙虚に充実した、日常生活が欠けていたのである。(「死と信仰 )
私は、石川氏とともに、「静かに緊張した、謙虚に充実した、日常生活」という言葉に強い感銘をおぼえる。氏は「阿鼻叫喚の戦場を体験した吉田が〈自分に欠けているもの〉として気づいたそれこそが、真の平和主義の要点だと思う」という。
こうしたところから、「平和主義とは、普段の生活すべてにおける、日常的な佇まいの問題なのである」「平和の要は、単に〈静かに緊張した、謙虚に充実した、日常生活〉という平凡で俗なるものなのである」といった言葉が紡ぎだされる。一言でいうならば、「平和とは俗の極み」(第8章のタイトルから)なのである。氏のこうした平和観に、私も共感をおぼえる。
平和とは、誰でも次のような社会状態を意味すると考えるだろう――戦争がない、差別がない、衣食住に困ることがない、教育や医療サービスを受けられる、生きがいをもてる…、こうした社会の状態が保たれていること。だが、このような人間にとって好ましい状態を望むということは、氏によれば「あくまでもこの世的な、現世的な欲望である。現実的な快楽の追究である」。ここからさらに、氏は、「平和」とは、清らかで聖なるものというよりは、「むしろ俗の極み他ならないはずである」と結論する。
いうまでもなく、人間は、限界・弱さ・矛盾などを抱えた存在である。氏は、このことを素直に受け入れるならば、「私たちに入手可能な平和というものは、俗の極みとしてのものでしかあり得ない」と考えるのが自然だという。
石川氏の戦争観と平和観
石川氏は、内村鑑三(写真右端)から大きな影響を受けているようである。戦争を「天災の一種」としても捉えていた内村は「人間の手によって戦争廃絶が成し遂げられるとは考えていなかった」そうである。彼は非戦論を唱え、戦争反対を主張していたが、その理由は「それが実際の戦争廃絶と平和構築に効果的だから」ではなく、「ただそれが神の前に正しいから」だという。
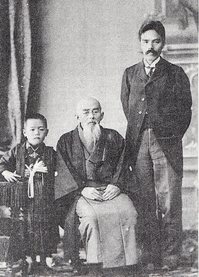 内村=右端(Wikipediaより) |
いずれにせよ、内村は非戦論を唱え、戦争反対を主張していたことは事実である。だがその一方で、彼は昔ながらの愛国心ももっていた。そして、日清戦争のさいの旅順港での日本軍の勝利を知ると、「隣近所全体にきこえるほどの大声」で「帝国万歳」を三唱したという。これは、誰の目にも明らかな矛盾である。しかし、氏によると、「正直な内村は、そうした自らの矛盾を十分に自覚することができていた。人間の理性や能力には限界があることを、ちゃんと知っていたのである」。だから、「最終的には、人間の手によって平和が実現されるという発想から離れて行った」のである。
こうした内村の生き方を肯定する氏の態度や、人間の弱さや不完全さを見つめる氏の視線を知ると、以下のような、戦争廃絶・平和実現に対して無力/消極的だと感じられる、氏の主張も理解できる。
まずは、戦争にかかわるものを挙げよう。
私たちは、暖かな眼差しで戦争を包み込み、受け入れるべきではないだろうか〔ただし、氏は決して単純な戦争肯定論者ではない〕。利害も、信仰も、プライドも、また正義感も、差別も、憎悪も、戦争の根源にあるものはみな、人間の内側から沸き上がるものに他ならないからである。
戦争は、拒否すべき対象ではなく、むしろ受け入れるべき対象である。真の戦争の克服は、平和平和と叫んだ時にではなく、むしろ戦争の醜さと、それを営む人間そのものが持つ矛盾や、葛藤や、限界を受け入れる勇気を持った時に、始まるのである。
つぎに、平和にかかわるものを挙げよう。
もし本当に平和への希望があるとするならば、それはセンチメンタルで人工的な平和主義のなかにではなく、むしろ、人間の失敗や、悲劇や、矛盾や、限界の呻きのなかにこそ、見出されるはずである。
究極の平和について、私たちは取り組み得ない。取り組み得ないものについては、祈る〔こと〕しかできない。戦争という人間的な営みを、徹底的に見つめ抜くことだけが、私たちに許されている「平和への希望」の佇まいである。
さらに、氏が「あとがき」の最後にもってきているのは、一般に聖フランチェスコの「平和の祈り」として知られているものである(註2)。そして、「真摯に平和を祈ること、これよりも大切な〈戦略〉はない」としている。
それでもやはり、平和を祈るという「戦略」だけで平和を実現できはずはないだろう。現実に、世界中で平和の祈りが捧げられているが、戦火は一向に止まないのである(註3)。「戦争を受け入れる」「平和については祈ることしかできない」というのでは、あまりにも無力ではないか? 多くの読者には、こうした疑念は拭いきれないに違いない。
氏は「真摯に平和を祈ることよりも大切な〈戦略〉はない」というのだが、ここでその「戦略」論に目を転じよう。
「戦略」とは平和構築のための手段である
石川氏は、クラウゼヴィッツ、モルトケ、リデルハートらの代表的戦略論を踏まえながらも、最も広義の「戦略」とは「最終的な目的を明確にし、それを達成するために、周囲の環境に合わせ、またのちの状況変化を予測しながら、広範囲で長期的な視点に立ってなされる行動の計画、およびその方針、である」とする。問題は「最終的な目的」は何かである。氏は、「闘争それ自体が目的化しないようにすること」が重要であるという。戦略は戦闘のみのためのものではないのだ。
ギリシア語の「ストラテゴス」「ストラテギア」という「戦略」(ストラテジー)の語源にも触れながら、氏は、「戦略を立てる」ことは決して「戦争をしようとすること」「戦いを望むこと」とイコールではない、という。いいかえれば、「〈戦略〉概念それ自体は決して好戦的な含みを持ったものではない」のだ。
では、戦略をどのように理解すればよいのか。ここで、氏は、平和と戦略を結びつけて次のように論じる――「〈戦略〉はむしろ、戦争を回避し、武力を用いないで済ますための方策や、戦後のより良い平和を構築する方策などを含んだ概念として、理解されねばならない」。こうした見解から導かれるのは、「〈平和思想〉と〈戦略思想〉は決して対立的な関係にあるのではなく、むしろ両者は同一の地平にある」という、一般人には意外な指摘である。
こうした主張はさらに敷衍されて、「戦争イコール戦闘なのではない」「どのように戦闘を回避するか、ということも含めて〈戦争〉を捉えるのが軍事思想であり、戦略思想なのである」と主張される。
「戦略」が以上のようなものであれば、戦略研究においては、人文学的な思索や探求も極めて重要な役割を担うことになる。すなわち、戦略を考えるさいには「その時代の人々の思想や、価値観や、佇まいを、敏感に察知していかなければならない」のだ。そして、その人文学的な知や思索というものは、人間の弱さや不完全さを深く見つめるものである。
たしかに、氏は具体的で明確な形で戦争廃絶や平和実現の手段を説いているわけではない。「戦争文化試論」というサブタイトルをもつ本に、そうした具体的な手段の提言を期待することは、ないものねだりかもしれない。だが、氏の構想している戦略論を彫琢することにより、弱い/不完全な人間が平和の実現に向かって、たとえ一歩であろうとも、歩みを進めることができるのではないか?(註4)
おわりに
最後に、本書の内容を一言でいうと、次のようになる。本書は、最近の戦争研究の流れのなかで、多岐にわたって自分の本音を分かりやすく包み隠さず述べた、一般向けの著作である。いずれにせよ、石川氏の「わずかにでも、皆であらためて戦争と平和について議論をするためのきっかけを作る」という目標は達成されるような気がする。
次回は、哲学者I・カントの『永遠平和のために』を取り上げ、カントの理想と現実世界のギャップについて論じる。さらに、平和についての議論を深めたい。
†
ブログのアップは毎月1日ですから、次回は元旦になりますね。
少々早いですが、良いお年をお迎えください。
星川啓慈(比較文化専攻長)
【註】
(1)http://www.let.hokudai.ac.jp/philosophy/religious-indian/staff-list-140.php
次のURLは、石川氏の講演(15分程度)である。本書のダイジェスト版ともいえる。http://www.youtube.com/watch?v=gL_de198QsE
(2)石川氏によると、この祈りは実際にはフランチェスコ自身の作ではないそうだ。また、これは第一次世界大戦のころから世界中に広まったらしい。
(3)私は祈ることは無駄であるとはいわない。自分でもそれに近い行為をすることもある。仮に実際の効果がなくとも、祈り続けるのが宗教のあるべき姿だと思っている。
(4)ただし、対立関係にある2つの集団が平和実現も考慮にいれて戦略を立てたとしても、2つの戦略が対立する場合も想定できる。この問題は解決が難しいかもしれない。極端な話だが、日本人にはあまり知られていないということもあるので、一例をあげておく(『戦争は人間的な営みである』30-35頁参照)。
1945年8月6日、原爆を搭載したB-29「エノラ・ゲイ」がテニアン基地を離陸する前に、プロテスタントのチャプレンであるW・ダウニー大尉が、乗組員を前にして「祈り」を行なった。その一部はこうである――「戦争の終わりが早くきますように、そしてもう一度地に平和が訪れますように、あなた〔神〕に祈ります。あなたのご加護によって、今夜飛行する兵士たちが無事にわたしたちのところへ帰ってきますように」。当時のアメリカにとっては、日本への原爆投下が「平和実現の手段」なのである。しかし、これは、われわれ日本人にとっては、到底受け入れることができない。なるほど、この祈りは首尾よく神に聞き届けられた。だが、多数の日本人が悲惨な死に方をした。この動かしがたい事実は、日本人から見れば、神義論で取沙汰される典型的な「道徳的悪」である。いいかえれば、キリスト教を信じない理由となろう。
平和実現の手段やそれに至る道筋が、対立する複数の集団間で同意を得られないことは、珍しくない。それには「視点」をめぐる難しい問題がある。それらの集団を包み込むような「包括的視点」を見出すことは、現実問題として、きわめて困難である。これと同型の問題は、日常的な出来事から始まって抽象的な哲学的議論に至るまで、随所にある。
【参考文献】
(1)石川明人『戦争は人間的な営みである――戦争文化試論』並木書房、2012年。
(2)石津朋之「解説――人類は戦争に魅了されている?」(M・クレフェルト『戦争文化論(下)』原書房、2010年、所収)。
(3)星川啓慈『対話する宗教――戦争から平和へ』大正大学出版会、2006年。
(4)田丸徳善ほか『神々の和解――21世紀の宗教間対話』春秋社、2000年。

