学部・大学院FACULTY TAISHO
比較文化専攻
戦争と文化(14)――「旧い戦争」と「新しい戦争」: M・カルドーの『新戦争論』から(1)
はじめに
前回のブログで予告したとおり、今回から、メアリー・カルドーの『新戦争論――グローバル時代の組織的暴力』(New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 2001)を取り上げます。
カルドーは序論に続けて、クラウゼヴィッツを批判する「旧い戦争」という章(第2章)を書いています。それほど、彼の影響が大きいということです。彼女いわく、「クラウゼヴィッツは、19世紀から20世紀に発展した戦略的思考の礎石を作った人物である」。彼の戦争論/戦争観を踏まえないと、カルドーのいう「新しい戦争」が理解できないのです。
歴史の流れと戦争の諸形態

あらゆる社会や時代には、それぞれに特徴的な戦争の形態があります。しかし、カルドーによれば、われわれが「戦争」として認識するもの、政策決定者や軍事指導者が「戦争」と定義しているものは、実際には、15世紀から18世紀のヨーロッパで出現した特殊な現象にすぎません――これもヨーロッパ中心のものの見方と関係しているでしょうね。
戦争は、①17-18世紀の絶対主義国家の権力増大にともなう比較的限定された戦争、②19世紀のナポレオン戦争やアメリカの南北戦争に見られるような「国民国家」の確立と関連した革命の一端を担うようなもの、③20世紀前半の総力戦(2つの世界大戦)、④20世紀後半の同盟間もしくはその後の東西陣営で戦わされたイメージ上の冷戦など、いくつかの段階を経てきました。カルドーは4つの段階を、①政治体制の種類、②戦争目的、③軍隊の形態、④軍事技術、⑤軍事経済という5つの観点から比較しています。
当然のことながら、歴史の流れとともに、戦争は段階ごとに異なる形態をとりましたが、その相違にもかかわらず、戦争はつねに「同一の現象」として受け取られてきました。すなわち、クラウゼヴィッツ的に、「戦争は、中央集権的で、〈合理的〉とみなされ、階層的に秩序づけられた領土にもとづく近代国家を建設するためのもの」と考えられてきたのです。しかしながら、カルドーは「われわれが考えているような形態の戦争は、時代遅れのものとなりつつある」と主張します。そのもっとも大きな原因は「政治体制」の変化でしょう。
18世紀頃の戦争
クラウゼヴィッツの定義では「戦争とは、国家の利益をめぐる国家間の戦争」でした。しかし、カルドーによれば、「国家活動としての戦争という概念が、確固たるものとして確立されたのは、18世紀末」のことでした。つまり、クラウゼヴィッツのいう「戦争」は、18世紀まで登場しなかったのです。
カントは「常備軍の撤廃」を『永遠平和のために』(1795年)で唱えたことを紹介しましたが(第11回目)、カルドーによれば、「国家の統制下におかれた常備軍の確立は、近代国家に固有な正統的な暴力の独占を実現するうえで、不可分な要素」でした。また、彼女がいうように、「戦争に訴える権利という神学から導き出された正義の観念にかわって、国家の利益が戦争を遂行する正当な理由」となりました。ここにも、宗教学でいう「世俗化」の一側面を見ることができるかもしれません。
このことと並行して、戦争行為にかんする諸規則が発達し、これらは「戦争法」として法典化されました。すなわち、「戦争行為は社会的に是認された活動であり、組織化され正当な理由をもたなければならない」という事実そのものが規則によって定められたのです。
ところで、太平洋戦争後の日本が奇跡的な経済的復興・成長を遂げたことの理由の1つとして、防衛/軍事につぎ込む予算がそれほど膨大ではなかったことを、あげることができるでしょう。これとは対照的に、カルドーによれば、18世紀には、ヨーロッパのほとんどの国々で軍事費が国家予算のなんと「4分の3」を占めるようになっていました。そこで、常備軍を維持する資金を確保するためには、行政・徴税・借入などを秩序立てる必要がありました。
そのためには、国家内において、法・秩序・正義を確立するのに必要な手段を見出さねばなりませんでした。現在の日本は、法・秩序・正義が比較的確立されていますが、当時のヨーロッパ諸国では、現在の日本ほどではなかったようです。そこで、君主は、資金を得るのと引き換えに、市民や旅行者などに「保護」(たとえば、強盗や暴力行為をはたらく者から身を護ってやること)を与えるという「一種の暗黙の契約」が成立しました。こうして、国王は戦争のための資金徴収能力を増大させることができるようになったのです。つまり、対外的な戦争のための準備ができるようになったのです。
この一方で、社会学者のA・ギデンスが指摘しているように、「国内においては平和の到来というプロセス」が起こっていました。これには興味を掻き立てられますね。というのも、対外的な戦争の準備が整えばととのうほど、国内は平和になるというのですから。また、次のことも興味ぶかいですね。現代においては、どこの国でも「警察」と「軍隊」が区別されていますが、この区別は、じつはこの頃から生じてきたそうです。つまり、国内の法・秩序に対して責任をもつ警察と、国外の敵と戦い国を守る軍隊とが、役割分担をするようになったのです。
もちろん、どの国においても以上のように話が進んだわけではありませんし、こうした分析には反論もあるでしょう。たとえば、ルソーは「好戦的な君主は、敵に対してと同様に自らの国民に対しても戦争を行うのである」と鋭い指摘をしています。現在のシリア情勢を連想する読者もいることでしょうね。
18世紀末における「戦争」概念の確立と、19世紀の戦争
いずれにせよ、18世紀末にいたって、「われわれが今日〈戦争〉として受け止めているような社会的に組織された特定の活動を〈戦争〉として定義づけることができるようになった」のです。さらに、カルドーが「とりわけ重要」としているのは、この時期にいたって初めて「戦争それ自体と平和との区別が生じた」ことです! 信じがたい話ですね。それまで「戦争と平和」という対概念が明確な形では存在していなかった…。しかしながら、「戦争」概念が明確にされて初めて、「平和」概念も明確になるというのは、納得できます。
こうして、多かれ少なかれ、それまでの「継続的であった暴力的活動」にかわって、戦争は「非連続的な出来事」となり、「市民社会」――日常の安全と国内の平和が保障され、法や正義が尊重される世界――へと徐々に進歩していく上での「逸脱行為」とみなされるようになったのです。
余談ですが、カントが『永遠平和のために』を書いたのは、18世紀の末の1795年でした。上のような脈絡に照らし合わせると、この著作の意義の理解がますます深まりますね。
そして、19世紀に発展した近代戦争は「国民戦争」であり、そこでは「規模」や「機動性」がますます強調されるようになりました。とりわけ鉄道と電信(通信手段)の発達がその背後にあると推測できます。そこで、巨大な軍事力の集合体を管理するための「合理的」組織や「科学的」理論がますます必要となってきたのです。こうした状況において、クラウゼヴィッツの『戦争論』がいかに大きな影響を与えたかは、もう述べる必要はないでしょう。
20世紀の戦争

20世紀の戦争の特徴を一言でいうなら、「総力戦」ということになります。カルドーは、20世紀の総力戦を4つの視点から分析しています。
①20世紀前半の戦争は総力戦であり、武器をとって戦い、あるいは、武器や軍需物質の生産を通じて戦争を支えるために、国民全体のエネルギーが大規模に動員されました。総力戦においては、「公的空間」が社会全体を取り込もうとするので、「公と私」の区別はなくなってしまいました。これに応じて、軍人と市民、戦闘員と非戦闘員との区別も瓦解し始めました。
②戦争がますます多くの人々を巻き込むようになると、国家利益の観点から戦争を正当化する説明が、かつては人々を納得させるような妥当性をある程度持ちえていたものの、ますます空虚なものとなってしまいました。そこで、国民の「共通の目標」や戦争の「正当性」などが必要になってきます。社会的に組織化された正統的暴力の場合ともなれば、個々の兵士が信じることができ、他者と共有できる共通の目標や正当性が必要となるのです。愛国心、民主主義の擁護、悪に対する正義の戦い…。しかし、こうした共通の目標や戦争の正当性がすべての場合において期待通り機能していたかということになると、多くの問題を指摘することができるでしょう。個々の兵士の気持ちというものは、やはり一人ひとり異なると推測できるからです。
それでも、「自分が殺されるかもしれない」という危険を背負わなければならない兵士が「英雄として扱われる」ということは、見逃してはならない点だと思います。カルドーの指摘では、たとえばベトナム戦争のさいには「兵士たちは自らを英雄だと感じることができなかった」といわれています。これと同種の指摘は、第5回目に登場した『戦争における「人殺し」の心理学』の著者グロスマンなどもおこなっています。アメリカでは、ベトナムからの帰還兵は、必ずしも、暖かく迎えられたわけではないのです。
③近代戦争の戦術の発展は、著しくその効用が損なわれる点にまで達しました。近代戦争においては、武器/兵器の革新/発明により、戦術/戦略がめまぐるしく変わってきました。現時点での、近代戦争における技術的革新の帰着点は、もちろん、大量破壊兵器/核兵器です(さらにいえば、サイバー戦争や宇宙戦争もありますね)。しかし、カルドーは「核兵器の使用を正当化しうる合理的な目標などあるだろうか?」と問いかけます。彼女は、核兵器は「近代戦争の大前提である国家利益それ自体を意味のないものにしてしまう」という見解を懐いているのでしょう。
④第二次世界大戦後、「同盟」が強固になったことにより、国内問題と対外問題の区別が曖昧なものとなりました。すでに、第二次世界大戦の時点でさえ、「個々の国民国家にとって単独で戦争を遂行することが不可能であること」が明白になっていました。現代世界でもさまざまな軍事同盟やそれに類するものが結ばれていますが、同盟を結んだ国の間では、軍事にかんする限り、国内と国外の区別がつきにくくなっているということです。
ちなみに、カルドーは「〔同盟による〕国境を越えた軍事力の統合が実際に戦争を抑制している」点があまり議論されていないことを指摘しています。
「新たな戦争」
カルドーは「公と私、軍人と市民、国内と国外の区別が瓦解しつつあることにより、戦争と平和の区別自体もまた疑問視されはじめている」と論じています。G・オーウェルは『1984年』で「戦争こそが平和である」と述べたそうですが、米ソの冷戦下でのことを考えてみましょう。おおまかにいえば、冷戦期には、「観念上の戦争」がひき続く一方で、「現実の戦争」は回避されました。オーウェルのいう「戦争」が「観念上の戦争」で、「平和」が「現実の戦争の回避」に相当するのです。
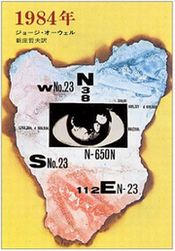
一般的に、冷戦については、次のよう解釈されています。①軍事同盟〔西側諸国と東側諸国〕によって統合された大規模な常備軍が維持されたこと、②技術的な軍拡競争が継続的にくりひろげられたこと、③平時としては過去に例を見ない規模の軍事支出が確保されたこと、こうしたことなどが平和を保障してきた、と。私なりに解釈すれば、「西側諸国と東側諸国が総力をあげて戦争を始めれば取り返しのつかないことになる」という認識が平和をもたらした、ということです。
ここで、カルドーは「新しい形態の戦争」について言及します。実際には、冷戦の間も、ヨーロッパふくめた世界各地で多くの戦争が勃発していたのです。そして、それらの戦争では、なんと「第二次世界大戦を上回る死者」――信じがたいですが、時間が長いためにそういうことになったのでしょう――が発生していたといわれます。
問題は「これらの戦争はわれわれの戦争概念にそぐわないものであったために、戦争として認識されていない」ことです! つまり、クラウゼヴィッツの戦争観に代表されるような戦争理解からすれば、これらの戦争は「戦争」(国家間での戦争)ではなかったということです。だからこそ、冷戦の間に勃発した戦争は「戦争」として認識されなかったのです。カルドーいわく、「冷戦の間は、東西対立が支配的であったために、新しい形態の戦争の特色は陰に隠れており、そうした戦争は、東西対立を中心とした対立構造の中で周辺的な部分を成すに過ぎない、と認識されていた」。
しかしながら、カルドーによれば、毛沢東とその後継者による太平洋戦争中の抵抗運動、ゲリラ戦を端緒とする20世紀後半の「非正規戦争/非公式な戦争」は、「新しい形態の戦争」の先駆だとされています。そして、冷戦が終焉する以前から、「新たな敵意」(ルトワック)と呼ばれるものが、登場していたのです。
おわりに
次回も引き続き、カルドーの「新しい戦争」を取り上げます。『新戦争論』は皆さんの戦争観に必ず影響を与えます。クラウゼヴィッツ的な戦争観で現代の戦争は理解できません!もしもそうなら、そのことは世界平和の実現にも影響を与えるでしょう。
このブログのアップは毎月1日ですから、次回は4月1日です。入学式の日ですね。
星川啓慈(比較文化専攻長)
【参考文献】
(1)メアリー・カルドー(山本武彦・渡部正樹訳)『新戦争論――グローバル時代の組織的暴力』岩波書店、2003年、とくに第2章。
(2)D・グロスマン(安原和見訳)『戦争における「人殺し」の心理学』ちくま学芸文庫、2004年。※同じ著訳者による『「戦争」の心理学――人間における戦闘のメカニズム』(二見書房、2008年)も実に読み応えのある重要な著作です。いずれブログで取り上げます。
