学部・大学院FACULTY TAISHO
比較文化専攻
戦争と文化(18)――戦闘における生理と心理: 戦闘という極限状態になると、人間の心や身体はどのような状態になるのか?
はじめに
第17回目の最後で予告した今回と次回のブログの内容を入れ替えて、今回は「戦闘における生理と心理」にさせていただきます。うかつにも、写真の貼りこみの順番を間違えてしまいました(苦笑)。
よく「何事も経験しないとわからない」といわれます。戦闘も経験しないとわかりません。驚くべきことに、死闘をくり広げた敵に、後になって「友情」のようなものを感じる場合もあるようです。たとえば、第二次世界大戦の退役軍人であるアメリカのクライトマンは、このように述べています――「戦闘のまっただなかに身を置いた人間は、堅い絆で結び付くんだ。味方だけじゃなく、敵ともだよ。それ以外の人間とは、たとえどんなに親しい間柄でも、あの絆は絶対に共有できないね」と。
生死をかけた激戦のあとですから、脈絡はまったく違うとしても、キリスト教の「汝の敵を愛せよ」という教えと、一脈通じるところがあるかもしれませんね。
いずれにせよ、戦闘など経験しないに越したことはありません。また、そうしたことに興味をもつことなく人生を終える人も多いでしょう。戦闘などについて考えたくもないという人もいるでしょう。
それでも、戦闘について知ることによって、得られるものがあります。それは、われわれの日常生活を見る目が変わるということです。
戦闘については、映画・インターネット・書物・兵士たちの証言などで、少しはご存じでしょう。凄惨な現実描写を紹介するよりも、ここでは、戦闘中の人間の生理や心理について見ていきます。グロスマンとクリステンセンの『「戦争」の心理学――人間における戦闘のメカニズム』を参照しながら、戦闘という非日常的で極限的な状況に追いこまれると人間はどうなるか、を考えていきたいと思います。

論理脳と野生脳
まず、暴力行為の予測・管理の分野における有数の専門家である、ディ=ベッカーが執筆した上の『「戦争」の心理学』の「まえがき」から始めましょう。彼は「こと戦争に関しては、頭より身体のほうが賢い場合がある」といいます。
人の脳が野生状態で〔生存のための〕実地試験に合格したのは、何百万年も昔のことである。その脳を私は「野生脳」と呼び、「論理脳」と区別している。論理脳をありがたがる人は多いが、いったん危機的な状況に陥ると、この脳はあまり役に立たない。論理脳は反応が遅く、独創性に欠ける。善悪の判断にこだわり、なかなか現実を受け入れられず、貴重なエネルギーを空費して、ものごとはどうあるべきか、かつてはどうであったか、どうでありうるかなどと考えてしまう。論理脳は、厳密な限界や規則を設けてそれに従いたがる。しかし、野生脳はなにものにも従わず、なにものも考慮せず、いかなる義務も負わず、必要とあればどんなことでもする。感情にも政治にも礼儀にも縛られない。野生脳の働きは非論理的に見えるかもしれないが、自然の摂理に適合するという点では100パーセント論理的である。ただ、論理を用いて人を納得させようとしないだけだ。事実、戦闘のさいには、人がなにを考えようが野生脳はいっこうに気にしない。…
たとえば、戦争の話で脚光を浴びるのはたいてい勇気だが、戦闘のさいには恐怖心も重要な役割を果たしている。恐怖を感じると、身体は行動に移る準備を開始する。四肢に流れ込む血液が増加し、筋肉の乳酸が燃え、呼吸数も心拍数も増大する。恐怖を感じるとアドレナリンが増えるのはよく知られているが、生き残りの確率を高めるために増加する物資はもうひとつある。それはコルチゾールという驚くべき物質で、これが増えると血液の凝固速度が上昇する。負傷したときのために備えているわけだ。
これを読むだけで、戦闘状態になると、脳の状態が変化して人間が変わること、勇気だけではなく恐怖心も重要であること、恐怖を感じた時にはコルチゾールが増加して負傷のさいの出血に対処するという人体のメカニズムのことなどもわかります。
いずれにせよ、戦闘状態は非日常的なものであり、われわれの日常生活とは対極にあるものです。そして、「こと戦争に関しては、身体は賢い」のです。
血管収縮
ディ=ベッカーの「四肢に流れ込む血液が増加する」ことは反対の例ですが、血管収縮についてお話ししましょう。
寒さでもストレスでも血管収縮は起きます。寒い朝に指がかじかむのは毛細血管が収縮するからです。血管収縮がさらに進むと、複雑な運動に必要な筋肉に血が流れなくなります。血液は身体の中心部分および大筋群にたまり、このため血圧が上昇します。身体の表層部は防護服さながらになり、動脈が傷つかないかぎり、かなりの損傷を受けても出血しにくくなります。
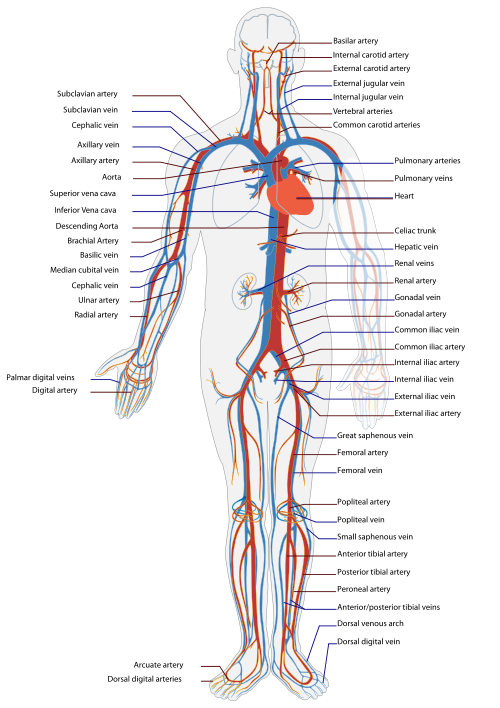
グロスマンによれば、これはどうやら「戦闘のさいに出血を抑えることで、生き残る可能性を高めるために発達してきた仕組みらしい」とのことです。しかし、血液が流れないと筋肉は動かなくなりますから、代償として、運動をコントロールする能力が失われます。さらに時間がたつと、今度は反動がきて、血管拡張という逆の現象がおきます。
ある警察官が、銃撃戦のあとで、自分の服の袖の上腕部分に小さな穴があいているのに気がつきました。彼はホッとして「危ないところで当たらなかったんだな」といいました。するとその時、腕の傷口が開いて、どっと血が噴き出しました。無事だと思って安心したせいで、血管収縮が終わって血管拡張が始まったのです。
さきのコルチゾールといい、この血管収縮といい、人間の種々の闘いの歴史は身体のメカニズムまで作り上げてきた、ともいえるのです。
大小の失禁
あまりきれいな話ではありませんが、厳しい訓練を受けた兵士たちは戦闘中に失禁するでしょうか。何しろ彼らは極限状態にあるわけですから、「失禁する兵士もいるだろう」という予想はつくでしょう。しかし、どのくらいの兵士が失禁するのでしょうか。もちろん、戦闘の激しさや個人の精神力など、考慮すべきことはいろいろとあります。
第二次世界大戦時のアメリカ軍の戦いぶりに関する公式報告書にある調査では、「第二次世界大戦で戦った米兵の4分の1が尿失禁の経験があると認め、12.5%は大失禁を経験したと認めている」そうです(『アメリカの兵士』)。「先鋒」に当たる兵士だけに注目し、激しい戦闘を経験しなかった兵士を除くと、その数はさらに上昇します。激戦を体験した兵士の約50%が尿を漏らしたことを認め、25%近くが大便を漏らしたということです。
さらに、大小の失禁をしたことを認めることを嫌がる兵士もいることは確実です。「恥ずかしい」「屈辱的なことだ」「メンツにかかわる」「自分は異常なのかもしれない」…。皆さんの中にも、恐怖や危険を感じた時の失禁の調査をされた場合、たとえ失禁したとしてもそれを認めたがらない人がけっこういるでしょう。だとすれば、現実には、右の数値よりもさらに多くの兵士が大小の失禁をしていると推測できます。
戦闘中に起こる多種多様な出来事に比べれば、失禁などは取るに足りないことです。くわえて、人体のメカニズムは戦闘状態となれば、身体にある不要な尿や便を排出するようになっています。多大なストレスがかかる、生きるか死ぬかの状況に直面したとき、下腹部に「荷物」が入っていれば、それは放り出されるようになっているのです。ですから、大小の失禁といえども、身体から見れば自然な現象なのです。
それでも、生死にかかわる戦闘の最中に失禁しそうになったときは、どうすればいいのでしょうか。薬物服用などのうまい手段があるのでしょうか。グロスマンがいうように、「そのまま闘い続けるしかない」のです。
戦闘における特殊な体験
戦闘に参加した兵士や、凶悪犯と銃撃戦をする警察官は、日常では経験しない種々の体験をします。トンネル視野(視野が絞られてくる)、明晰視(物事がはっきりと見えてくる)、聴覚の低下(音が聞こえなくなる)、聴覚の増強(耳が研ぎ澄まされてくる)、時間延長(物事がスローモーションで見えてくる)、時間短縮(物事がファストモーションで見えてくる)などです。状況により、兵士たちは正反対の体験をしますが、いずれにしても日常生活ではほとんど起こらないものばかりです。また、これらは同時に生じる場合もあります。
以下では、このうちトンネル視野(視野狭窄)について簡単に紹介し、そのあとで選択的感覚抑制・聴覚抑制について見ていきましょう。そして、それらに続いて、ストレスの問題に目を移したいと思います。
トンネル視野
ある調査によれば、アメリカの警察官の10パーセントは、銃撃戦のさいにトンネル視野を体験しているそうです。これは、銃撃戦などで過大なストレスにさらされると、「目が焦点をむすぶ範囲が狭くなって、まるで筒をのぞいているかのように感じる現象」です。「トイレットペーパーの筒をのぞいているみたいだった」「拳銃を握る男の手の、指に嵌った指輪しか見えなかった」などと報告されています。

あるSWAT(特別攻撃隊)隊員は、ショットガンで武装した容疑者と格闘したときの体験を、次のように語っています。
私たちはふたりとも片手で同じショットガンの銃口をつかみ、片手で同じ引き金をつかんでいました。トンネル視野を体験した人はみんな、トイレットペーパーの筒をのぞいているみたいだったと言うけど、私の場合はソーダのストローをのぞいてるみたいでしたよ。
このSWAT隊員は、さらに聴覚抑制も同時に体験しています。
そうやって、ショットガンを奪いあっていたとき――ズドーン! その12番径が私たちの顔のあいだで火を噴いたんです。目の前で12番径が火を噴いたんですから、ふつうならこんなにやかましいことはありませんよ。それが心底仰天したですがね、私にはその音が聞こえなかったんです。あとで耳鳴りすることもありませんでした。
この隊員のように、トンネル視野と聴覚抑制の両方を体験する事例は、ほかにも数多く報告されています。
選択的聴覚抑制
競技射撃の全米優勝者・警察分野のライターなどの肩書きをもつアユーブは次のように述べています。
これまで見てきたことから考えて、選択的聴覚抑制は(トンネル視野も)だいたいにおいて大脳皮質の知覚の問題だと思います。耳は聞こえ、目は見えていても、生き残るという最大の目標に集中しているため、その目標に無関係と思われる情報を大脳皮質が意識からはじいているのです。
私はこの原稿をかなり集中して書いています。周りの音はほとんど気にならず、きつめのズボンのベルトも気になりません。感覚器官による情報を全部処理していたら、脳はパンクしてしまいます。脳は、われわれがキャッチする情報のほんの一部しか処理しません/処理できません。脳は、種々の状況において、それほど重要でない感覚刺激を無視するようになっているのです。
銃撃戦などの過大なストレスのかかる状況では、感覚の選択的遮断という現象がさらに徹底され、生き残るために必要な感覚以外はすべて遮断されることがあります。
通常、その生き残りに必要な感覚とは視覚ですが、光量が足りずに相手が見えない時には、聴覚の「スイッチ」が入り、視覚の「スイッチ」が切られることがあります。身体が聴覚によって敵を捉えるようになるのです。この場合、「銃声は聞こえるが、銃口から火が噴くのは見えにくく」なります。もちろん、その反対に、敵や凶悪犯に視覚的にロックオンしたときには、聴覚のスイッチが切れ、視覚のスイッチが入ることもあります。
しかし面白いことに、聴覚のスイッチが入り視覚のスイッチが切られる場合のことですが、発砲したあとで耳鳴りしないこともあるそうです。つまり、聴覚のスイッチが入っている時でも、音が遮断される可能性があるのです。それは、以下のような身体のメカニズムに理由があります。
聴覚科学の研究によれば、まぶしい光を瞼で遮断できるように、耳にも大きな音を物理的・機械的に遮断する機能が備わっているようです。この自動的・機械的な音の遮断は、突然の大音響の衝撃波の立ち上がりに反応して、1ミリ秒以内起こります。銃を発射して大きな音が出るとき、耳が過度な刺激を受けますから、銃声の「衝撃波の立ち上がりの瞬間」に自動的に耳を聞こえなくすればよい、というわけです。素晴らしい身体保護のメカニズムですね。
兵士の間には「当たったときには聞こえない」という言い伝えがあるそうです。戦闘機による爆撃を受けた兵士、ロケット弾を被弾した兵士、迫撃砲の砲弾を受けた兵士、仕掛け爆弾が爆発した兵士…。こうした体験をした兵士の多くは、みな同じことをいうそうです。つまり、自分のすぐそばで爆発があって、身体が吹っ飛ぶほどの衝撃を受けたのに、その爆発音は聞こえなかったし、耳鳴りもしなかった、と。爆発で両脚を吹っ飛ばされたにもかかわらず、耳鳴りもせずに、すぐに携帯電話で連絡をとったという警察官もいます。
彼らには、噓をいう必要はまったくありません。一種の選択的聴覚抑制によって、本当に「当たったときには聞こえない」のです。もちろん、すべての場合にこうだというのではありません。
また、小部隊の指揮官たちには昔から知られていたことですが、兵士たちには「戦闘中には大声で話しかけられても聞こえない」ということもあります。歩兵の射撃部隊の指揮官は部下の正面に立っていることが多いそうです。それは、好きでそこに立っているのではありません。部下の正面はもっとも危険な場所ですから、指揮官といえどもそこには立ちたくありません。しかし、部下に命令を聞かせたり、自分に目を向けさせたりするためには、指揮官は部下の正面に立っていなくてはならないのです。そうしないと、部下に大声で命令しても、銃撃に集中している部下には聞こえないのです。
以上のような聴覚抑制現象も、興奮のレベルやストレスのレベルなどの違いによって、また、状況の相違などによって、さまざまな形で現われます。いずれにしても、信じがたい報告がいくらでもあります。
戦闘とストレス
以下では、主としてアメリカ兵の話をしますが、1つだけ指摘しておきたいことがあります。それは「アメリカ軍は第二次世界大戦の前までは戦闘経験が乏しい」ということです。戦闘経験が豊富なドイツ兵やイギリス兵と比べると、アメリカ兵は戦闘のストレスに弱かったかもしれません。
第一次世界大戦・第二次世界大戦・朝鮮戦争に従軍したアメリカの兵士の場合には、「戦闘中に命を落とした兵士よりも、精神を病んで戦線から離脱した兵士の数のほうが多い」そうです。読者の皆さんはどのように思われるでしょうか。直接的な敵対行動で命を落とす兵士よりも、戦闘のストレスによって衰弱する兵士のほうがはるかに多かったのです。いくらなんでもそれは事実と違うのではないか、と感じるかもしれません。
しかし、第二次世界大戦の時には、兵士の発砲率は10-15%でしたから、多くの兵士は「人を殺したくなかった」わけです。そのうえ、体験したことのいない極限的な恐怖に長いあいだ襲われ、過大なストレスにさらされるわけです。そうだとすると、上の事実にも納得がいくのではないでしょうか。
第二次世界大戦中のこうした現象にかんする論文(「失われた師団」)では、驚異的な数字が示されています。その論文は「精神的衰弱によってアメリカ軍は50万4000人の兵士を失った」と結論しています。もちろん、「失った」というのは、「戦列を離れた」という意味で、必ずしも「命を落とした」ということではありませんが、驚くほどの数字です。
グロスマンが参照した『精神障害の診断と統計の手引き』――通称「DSM」とよばれ、何度も改訂されています――には、「ストレスの原因が人為的なものの場合、心的外傷(トラウマ)はより重く、長期にわたることが多い」と特記されています。東北大震災がありましたし、例外もあるでしょうけれども、基本的に自然災害や事故の場合には、「心的外傷後ストレス(PTSD)は、戦闘・強盗殺人などの人為的な場合と比較して多くなく、その程度も軽い」といわれています。
生命にかかわることであっても、それが人によって引き起こされた場合とそうでない場合では、かなり異なるということです。グロスマンがいうように、「ほかの人間によって恐怖や苦痛がもたらされた場合、人はショックを受け、打ちのめされ、人生を滅茶苦茶にされる」ということです。大きな負傷をするのなら、私も激戦で負傷するのではなく、不慮の事故で負傷したいと思います。多くの皆さんもそうでしょう。
戦闘の長期化と精神障害
古代の戦争の場合、実際の戦闘時間は短くて、勝敗は1時間程度で決まることもありました。しかし、戦闘は時代とともに長引くようになりました。戦闘が昼夜を分かたず続き、ぶっ通しで何週間も何か月も続くようになったのは、第一次世界大戦以降のことです。交替制によって、定期的に休息をとれればまだよいのですが、そうでなければ兵士にとっては耐えがたい状況となります。
第二次世界大戦のさいのノルマンディー上陸作戦のさいには、「後方」というものがなかったので、アメリカの兵士たちはまる2か月間、たえまのない戦闘とたえまのない死の恐怖から逃れることができませんでした。
このときに分かったことがあります。それは、「継続的な戦闘状態が60昼夜続くと、全兵士の98&が精神的戦闘犠牲者になる」ということです。残りの2%には「攻撃的社会病質者」も含まれますから、ほとんどすべての人間は、そうした状況で精神的戦闘犠牲者になるのです。60昼夜ももたない兵士がいることは想像に難くありません。60日どころか、1日で参ってしまってしまう兵士がいても、不思議はありあません。
同じく、第二次世界大戦のさいのスターリングラードの戦いは、およそ6か月にわたって続きました。ロシアの報告によると、一般のロシア人男性は60-70歳代まで生きるのが普通なのに、この戦いに参加したソ連軍の復員兵は40歳前後で死亡しています。
どうしてでしょうか。それは、この戦いを経験した兵士たちは、過酷な6か月間、1日24時間たえまないストレスにさらされ続けていたからです。戦争が終わっても、この戦いで蓄積されたストレスが極端に寿命を縮めたのです。戦争が終わったからといって、ストレスが消滅してしまうわけではありません。それはもうすでに兵士の身体と精神を蝕んでしまっているのです。

話は横道にそれますが、ロシア人男性の平均寿命は、1963年から2010年までの間で、最高が1986年の64.8歳で、最低が1994年の57.6歳です。彼らはかなり寿命が短いといえます。原因の一つが、真面目な話、ウォッカの飲みすぎともいわれています。復員した兵士たちは、ストレスから逃れるために、人並み以上にウォッカをあおったかもしれませんね…。
いずれにしても、戦闘が引き起こすストレスには、それを体験したことのないわれわれには想像を絶するものがあります。
おわりに
実際の戦闘に即した議論はしませんでしたが、戦闘中の特殊な体験やストレスの影響について述べました。
日常生活を平々凡々と生きているわれわれには、凄惨な戦闘についての実感をともなった理解は不可能です。それでも、戦闘中には身体全体が特殊な状態になるということは、それなりに理解できると思います。
私は、そうした異常な体験をすることなく、平凡な日常を生きることの幸せをつくづくと感じます。
星川啓慈(比較文化専攻長)
【参考文献】
(1)『「戦争」の心理学――人間における戦闘のメカニズム』(安原和見訳、二見書房、2008年)
